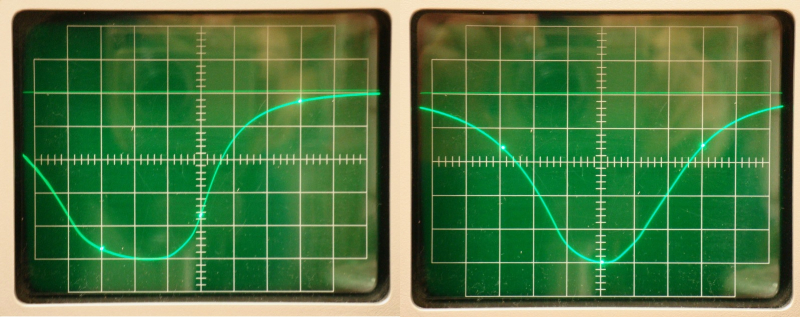NEC 7石AMラジオ NT-7P
 |
NECの最初期ごろのラジオです。13年前にヤフオクで入手しました。
説明では動作するとのことでしたが、確認すると無音の不動品でした。
ノイズも聞こえません。回路図は入手できるので、復活させることにしました。
TR構成:ST172(CONV), ST162(IFA), ST162(IFA), ST301x2(AFA), ST301x2(PWR)
Diode :SD-46(DET)
発売日:1957年(昭和32年)頃
入手日:2011年12月
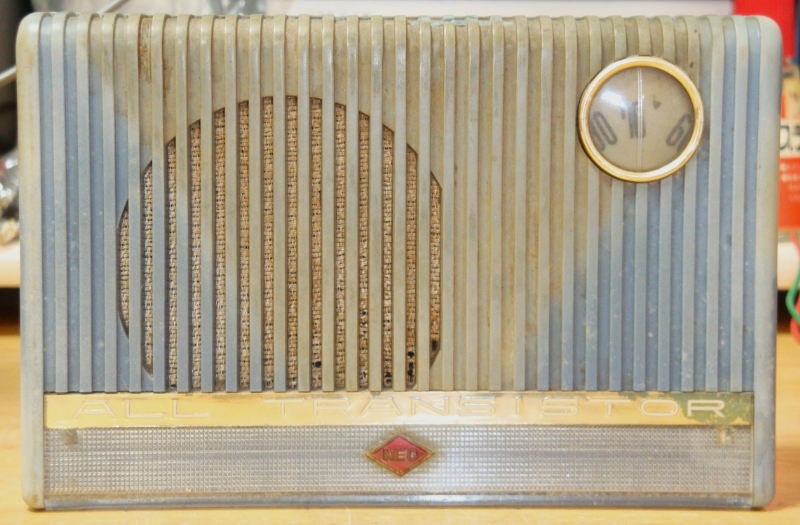 |
皮ケースの後がくっきりと分かります。かなり日焼けして退色しています。
カタログでは、サンゴ、オリーブ、ブルーグレーの3色ありますので、これは
ブルーグレーだったようです。ケースもかなり破損しています(後述)。
 |
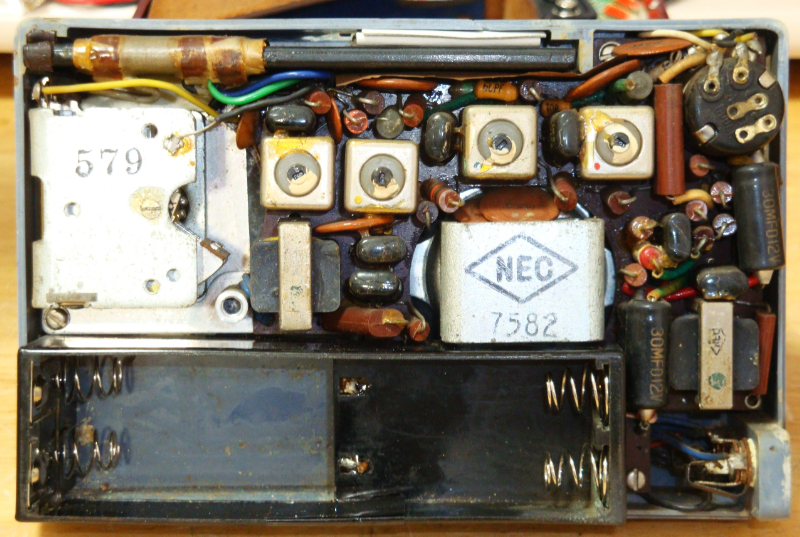 |
リアパネルを外したところ。NECの扁平型トランジスタが使われています。
006P電池ではなく、単三乾電池6本で9V電源としています。
外部電源を接続してみましたが、まったくの無音で、消費電流も30mA以上流れます。
電池端子が奇麗ですが、液漏れによる腐食で交換したようです。
 |
修理のため基板を取り外しました。電池が液漏れした跡があります。
 |
動作確認のため、バリコンとスピーカーは基板に接続しておきます。
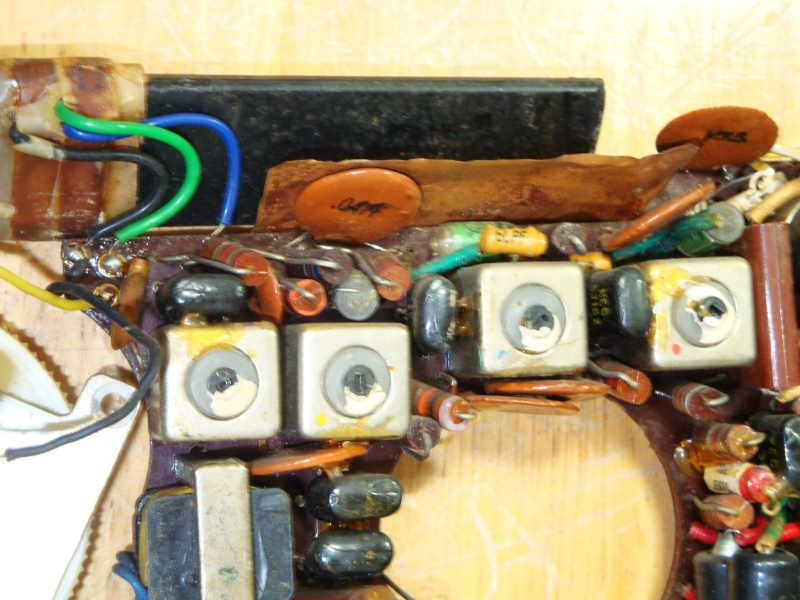 |
バーアンテナと基板回路をシールドするために薄い銅板がはんだ付けされています。
いかにも初期らしい製品です。
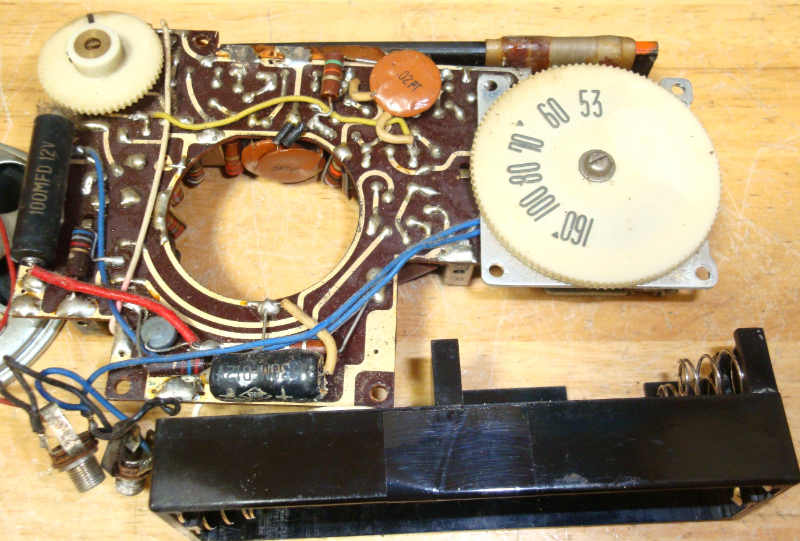 |
基板のはんだ面は、こんな感じです。ケミコンは完全に劣化しているので
交換が必要です。
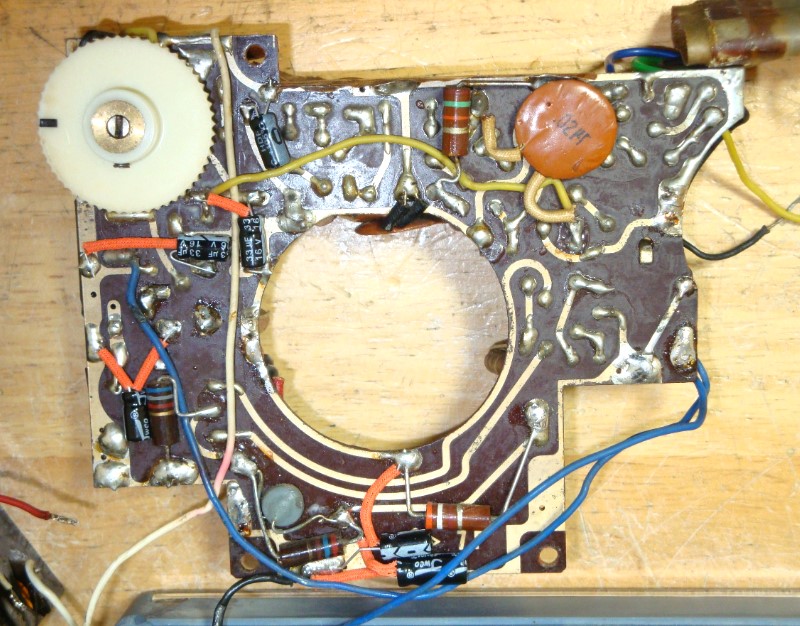 |
部品面のケミコンを交換すると、大きさがとても小さくなるので、見た目が変わります。
できるだけ雰囲気を残すため、すべて半田面に取り付けました。
ケースやスピーカーのフレームにぶつからないように、注意して取付位置を考えます。
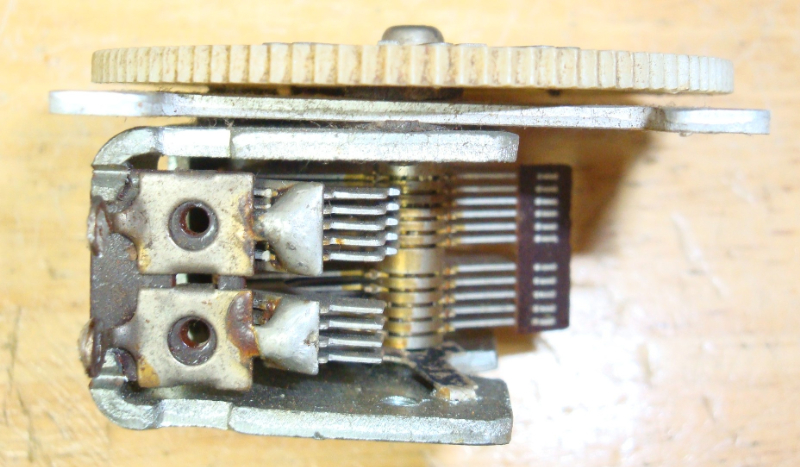 |
基板の次はバリコンの修理です。ゴムブッシュが溶けてつぶれています。
上がRF同調用、下が局発用です。
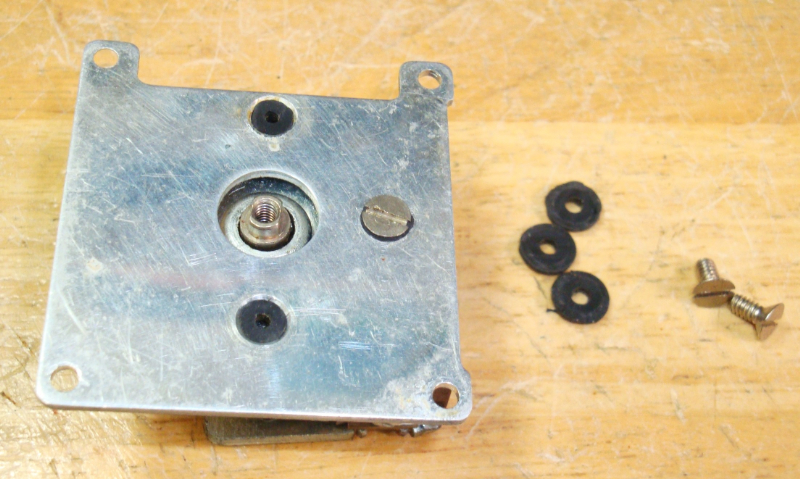 |
最初は、普通にゴムブッシュを付けましたが、高さが高すぎて、ネジが止まりません。
フレームの表面側をカットして、皿ネジの頭がフレーム面とフラットになるように
しました。
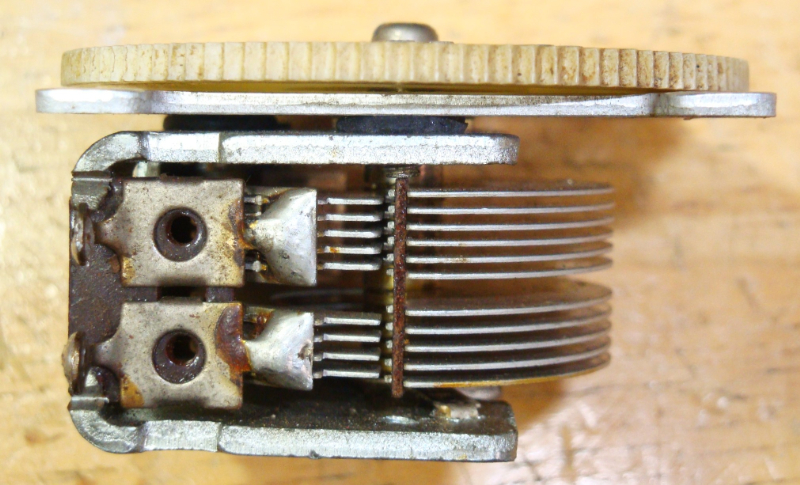 |
こんな感じですが、これでもダイヤルがフレームとぎりぎりです。
仕方がないので、最終的には、バリコンの軸部分にワッシャを1枚かませて、
ギャップを確保しました。
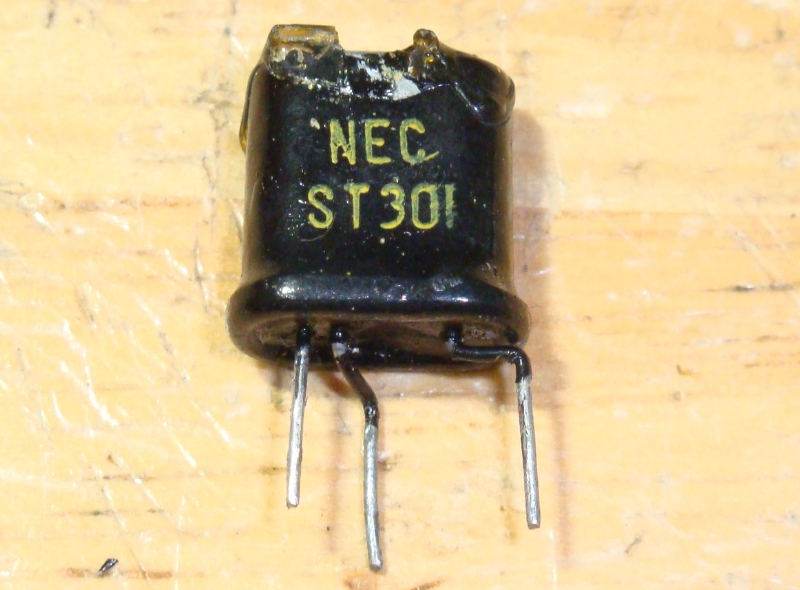 |
扁平型トランジスタは、すべてソケットに差し込むようになっています。
特性が安定していなかった時代なので、選別していたのでしょう。
ソケットに合うようにリードは加工されています。これでは振動で抜けてしまうため、
接着剤で他の部品に固定されていました。
参考までに、hFEは27〜46とばらついていましたが、動作は問題ありません。
回路図と比較すると、トランジスタは次のように改良されています。
ST-16B==>ST172, ST-16A==>ST162, ST-3B==>ST301
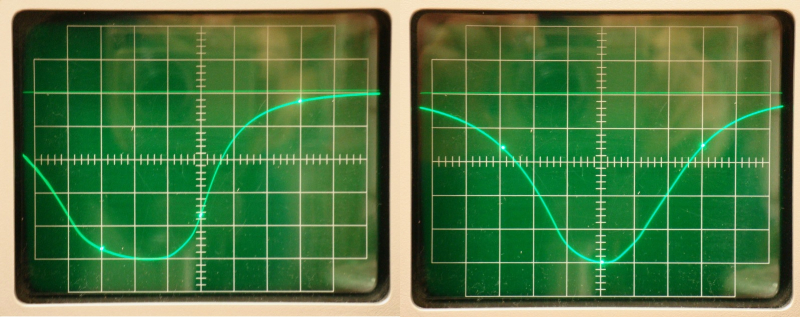 |
結局、無音の原因は、低周波段のカップリングコンデンサの容量抜けでした。
一通りの部品交換が完了し、消費電流を確認すると約10mAに下がりました。
ここから、調整に入ります。
先ずは、IFTの調整からです。写真左は調整前で、455kHzから相当ずれています。
右側のように、センター455kHzに合わせ込みました。
次に目盛合わせと、トラッキング調整を行って完成です。
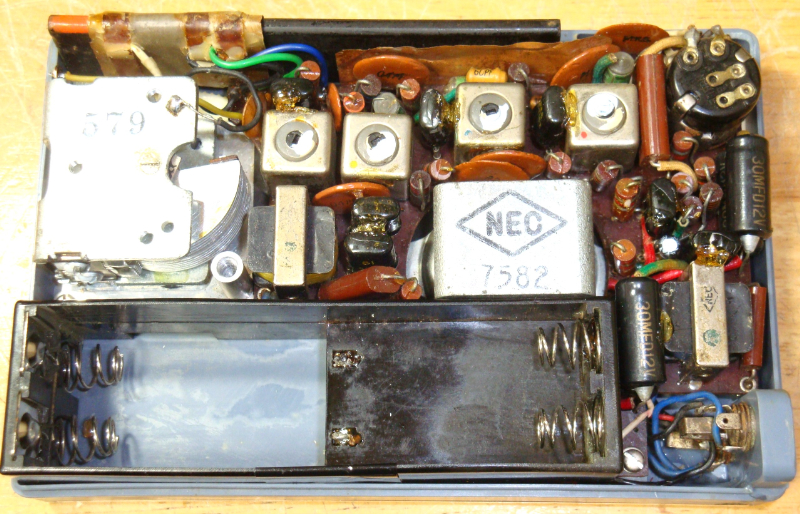 |
最終状態の基板の様子です。カップリング以外のケミコンは飾りで残しています。
これがないと、オリジナルの雰囲気が出ません。
回路図では電源スイッチがプラス側ですが、実機ではマイナス側に入っていました。
修正した様子は見られないので、回路図とは違っていたようです。
 |
交換した部品です。真ん中の白いケミコンが、カップリング用のコンデンサです。
元々基板のはんだ面に付いていたケミコンは、この2個だけでした。
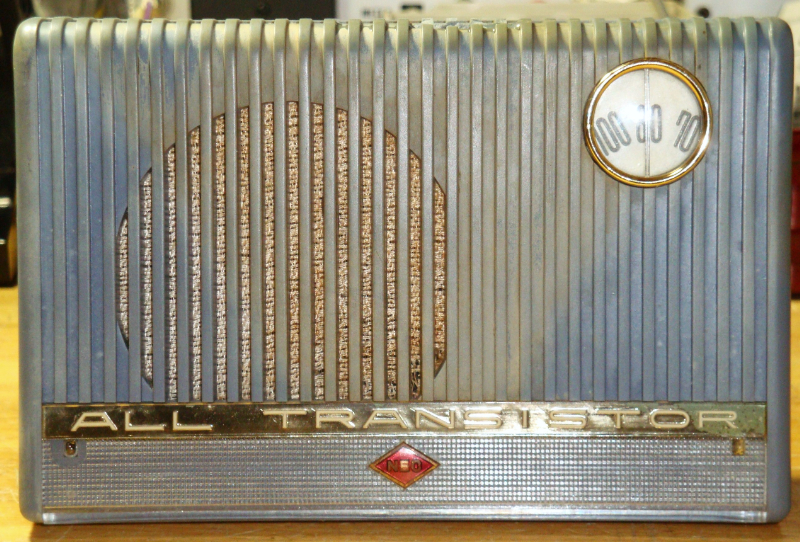 |
ケースを水洗いして、少しは奇麗になりました。ケースの破損個所も接着しています。
感度も問題ないレベルですが、音質は硬い音です。もう少し低音を強調しても
良いような感じですが、60年以上前のラジオが復活したと思えば満足のいく結果です。
 |
皮ケースを付けるとこんな感じになるのですが、悪いことに、ホックがケース上部に
あるため、その部分が大きく破損しています。
おそらく、ホックを止めるときに、強い力が加わって割れてしまったのではないかと
予想できます。或いは、ホック部分を落下させたのかもしれません。
いずれにしても、この位置に大きなホックを配置したのは失敗です。
2025年3月19日

Copyright(c) 2025 Hiroyuki Kurashima All Rights Reserved
←メニューへ
|